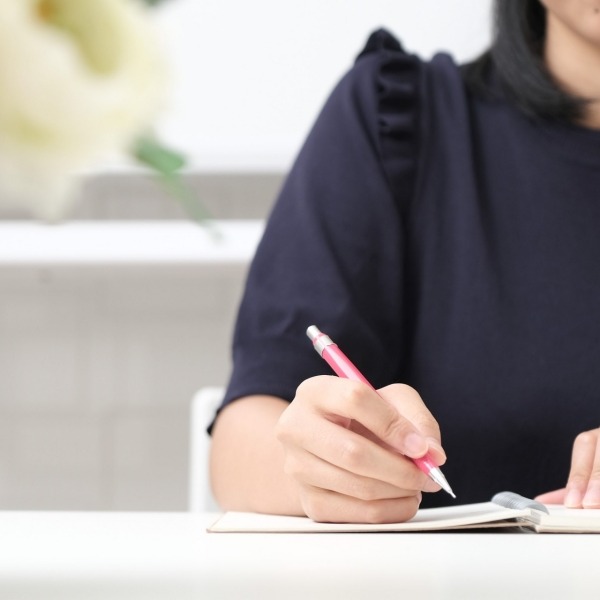【老後のお金】人生のお金事情-老後編
安心して暮らすために今から考える老後資金の話
はじめに:老後資金の準備、なぜ「今」考える必要があるのか?
私たちの寿命は延び続けています。日本は世界屈指の長寿国となり、「人生100年時代」とも言われるようになりました。2024年現在、男性の平均寿命は約81歳、女性は87歳を超えており、90歳、100歳まで生きることも珍しくなくなりました。
これは喜ばしいことですが、同時に、老後という「長い時間」をどう経済的に支えるかが、多くの人にとって現実的な課題になっています。
老後に必要なお金は、生活費だけではありません。医療費、介護費、住まいの維持費、趣味や旅行などの活動費まで含めると、思っている以上に多くの費用がかかります。
「退職したら、あとは年金で暮らせる」
そう考えていた時代は、もはや過去のものです。現在では、自助努力によって老後資金を準備しておくことが必要不可欠となっています。
この記事では、「老後にどのようなお金がかかるのか」「いくら必要なのか」「どう備えればよいのか」など、知っておきたい情報をわかりやすく整理してお伝えしていきます。

老後の生活費はいくら必要か?目安と内訳を知る
老後の生活費は人によって大きく異なりますが、まずは平均的なデータをもとに考えてみましょう。
総務省の家計調査によると、高齢夫婦世帯(夫65歳以上、妻60歳以上)の平均生活費は月約23万円。
一方で、もらえる公的年金の平均額は夫婦で月約20万円前後です。
つまり、平均的な家庭でも月3万円程度の赤字が出る可能性があるのです。年間にすると36万円、30年暮らせば1,000万円を超える差となります。
さらに、持ち家か賃貸か、地方か都市部か、趣味の有無、医療費・介護費の状況などによって、必要な生活費は上下します。
老後の生活にかかる主な支出項目は以下のとおりです:
-
食費、水道光熱費、通信費などの日常生活費
-
健康保険料、医療費、薬代
-
住宅費(賃貸の場合)・修繕費・リフォーム費用
-
介護に関する費用(ヘルパー、施設利用など)
-
交際費、レジャー・旅行費、趣味活動
-
税金(住民税、固定資産税など)
これらの支出をまかなうには、公的年金だけでは足りないケースが多く、事前の備えが必要です。
老後資金はいくら必要?「2,000万円問題」を超えて考える
2019年、金融庁が発表した報告書により、「老後に2,000万円の蓄えが必要」という言葉が一気に広まりました。実際には「老後30年間で毎月5万円の赤字が出る場合、約2,000万円不足する」という内容でした。
しかしこの「2,000万円」という金額はあくまで一例であり、すべての人に当てはまるわけではありません。
たとえば:
-
自営業の人は厚生年金がなく、受け取れる年金額が少ない
-
長寿家系で90歳以上まで生きる可能性が高い
-
老後も持ち家がなく、家賃を払い続ける必要がある
-
両親の介護や扶養を担う立場にある
このような条件がある人は、2,000万円では足りない可能性が十分にあります。
逆に、持ち家があり、健康で生活にお金をかけないという人は、2,000万円も必要ないかもしれません。
大切なのは、自分のライフスタイルに合った「必要老後資金」を正確に把握することです。
老後資金の準備方法:今からできることを始めよう
1. つみたてNISAやiDeCoの活用
長期的な資産形成には、国の制度を活用することが非常に有効です。
つみたてNISAは、年間一定額までの投資利益が非課税になる制度で、2024年からは新NISA制度によりさらに使いやすくなりました。長期・分散・積立が前提のため、老後資金づくりに適しています。
**iDeCo(個人型確定拠出年金)**は、積み立てた掛金が全額所得控除になり、税制優遇を受けながら老後の年金を自分で作る制度です。原則60歳まで引き出せないという制約はありますが、そのぶん確実に「老後専用資金」として積み立てることができます。
2. 生活の固定費を見直す
老後資金の準備は、収入を増やすことだけではなく、支出を減らすことも重要です。今のうちから生活の無駄を見つけ、固定費(保険料、通信費、サブスクなど)を見直すことで、将来への貯蓄に回す余力をつくり出せます。
特に、過剰な保障がついた保険や、不要な定額サービスは、年間にすると大きな金額になります。
公的年金のしくみを正しく理解しよう
老後の生活資金の柱は、やはり「公的年金」です。年金制度はよく「不安」と語られますが、仕組みを正しく理解していれば、むやみに恐れる必要はありません。
国民年金と厚生年金の違い
-
国民年金(基礎年金):自営業者やフリーランスが対象。
-
厚生年金:会社員や公務員が加入する上乗せ制度。
厚生年金は給与に比例して受け取れる額が増えるため、会社員の方が年金額が多くなります。
また、年金は「繰り下げ受給」が可能です。65歳からの受給開始を1か月遅らせるごとに、年金額が0.7%増加し、最大で84歳から受け取ることで年金が42%増額されます。
医療と介護:高齢期特有の出費に備える
老後は、生活費以上に医療・介護の支出が大きくなる時期でもあります。医療費は年齢が上がるごとに増える傾向にあり、病気の長期化や通院の頻度増加が原因です。
日本には高額療養費制度や、後期高齢者医療制度がありますが、それでも差額ベッド代や自由診療など、自己負担が発生する場面はあります。
介護費についても、介護保険があるとはいえ、要介護度が上がれば自己負担額も増え、訪問介護・施設利用・リフォーム費用など、トータルで年間数十万円から百万円単位になることもあります。
これらの支出に備えるためには、「医療費積立」や「介護保険」「がん保険」「医療特約」などを検討することも大切です。
老後も「働く」という選択肢も
近年では、定年退職後も働き続けるシニア世代が増えています。老後資金の不安を少しでも減らすため、「年金+アルバイト」や「フリーランスとしての活動」「資格を活かした仕事」など、柔軟な働き方が求められています。
企業も、65歳以上の再雇用制度を整備しており、70歳まで働ける環境も広がりつつあります。
「健康で働けるうちは働く」という姿勢が、経済面だけでなく、社会とのつながりや生きがいにもつながります。
まとめ:老後の安心は“今”の積み重ねから生まれる
老後の生活を豊かに、そして安心して過ごすためには、長期的な視点と計画性が欠かせません。
-
老後資金はいくら必要か、どのように使うかを“自分の言葉”で把握する
-
年金や医療・介護制度など、使える制度を正しく知る
-
できる準備を、今すぐ少しずつ始める
-
働き方や生活の選択肢を柔軟に考える
老後の不安を完全にゼロにすることは難しいかもしれませんが、「備えのある人」ほど、その不安を小さくすることができます。
未来の安心は、今日の一歩から。
本記事が、あなたの老後の備えを始めるきっかけとなり、人生100年時代を前向きに生き抜くための道しるべとなれば幸いです。
※「老後準備チェックリスト」「収支シミュレーション表」